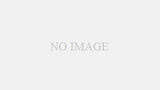ここに書かれている歴史は真面目に研究したものでは無いので話半分で。
古代~中世
宗教的な断食や治療的な食制が主。古代ギリシャ・ローマでは食事療法の考え方があり、ヒポクラテスらが体質と食事の関係を論じた。
18~19世紀
産業革命で食生活が変化。肥満が医学的関心を集め始め、「太り過ぎ=病気」とみなす考えが出る。ウィリアム・バンティング(William Banting)のダイエット帳(19世紀中頃)は“肥満対策”として有名。
20世紀前半
カロリー計算や摂取カロリーと消費カロリーの考え方が普及。第一次・第二次世界大戦の配給も食生活に影響。
1950-80年
脂肪(特に動物性脂肪)と心血管疾患の関連が注目され、低脂肪志向が広がる。公的な栄養ガイドラインも登場。
1990-2000年
低脂肪一辺倒への反動で低炭水化物(ローカーボ)ダイエットが再評価。市販プログラム(例:ダイエット企業、ミールプラン、体重管理プログラム)が拡大。
2010-現在
ケトジェニック、パレオ、インターミッテント・ファスティング(断続的断食)など多様化。スマホアプリ、ウェアラブル、遺伝子/腸内細菌研究による「個別化(パーソナライズ)」の流れ。医療的治療(外科的減量手術や薬物療法)の進展も。
まとめ
ダイエットは「食事制限」ではなく「生活の工夫」として古代から続いている。
流行は変わっても、基本原理はシンプル(摂取と消費のバランス)。
現代は科学とテクノロジーを駆使しながら、自分に合った方法を見つける時代へ。
裏まとめ
運動しないで痩せようとする愚か者多すぎる。(わいもそう)
高校生の時の弁当は米の代わりに卵焼きにしてた。めっちゃ良かった。食べたあともそんなに眠くならなかった気がする。
今までバランス悪い食生活してるからデブ。バランス良い食生活、適度な運動、睡眠これで痩せれる。わかっているのに現代は食が発展しすぎて美味いもんが多すぎる。
それを我慢しろって無理だろ。
米は朝昼夜どこか1回、タンパク質とる、運動。これだけでかなり減量できるよ。間食なんてダメだよ。