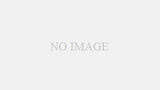わいの考察
このことわざって昔の人が駄々をこねるこどもに言い聞かせるために作られた言葉なんじゃないのか。
昔は10人兄弟とかおったらしいし、兄弟喧嘩もよくあっただろ。そんな中、「なんでわいが最後に選ぶんや!ぎゃおーん」ってこどもに少しでも理解してもらうために言ったのが起源やろ。
ChatGPTに聞いてみた
日本の古い食文化に由来
もともとは食事の場やお供え物の習慣から生まれたといわれています。
昔の日本では、神仏に食べ物をお供えしたあと、その「お下がり(残り物)」をいただく習慣がありました。
この「お下がり」には神様の霊力(福)が宿っていると信じられていたため、
「残り物=神様の福を分けてもらったもの」
と考えられていたのです。
この考え方が転じて、
「残ったものをもらうことは悪いことではなく、むしろ福がある」
という意味のことわざになりました。
平安~江戸時代の文献にも類似表現
はっきりした初出は不明ですが、
江戸時代のことわざ集『故事ことわざ集』(江戸後期)や『俚言集覧(りげんしゅうらん)』などに類似の表現が見られます。
これらの中では、食べ物や贈り物の「残り物」に幸福や縁起を見出す内容が書かれています。
神道的・仏教的背景
- 神道では「お供え物のお下がりをいただく=神様の恵みを受ける」
- 仏教では「他者に譲る心=功徳(くどく)を積む」
この両方の思想が混ざり、
「残り物には福がある」という言葉が広まりました。
裏まとめ
テストで3点問題なら△1点くらいもらえるやろ。